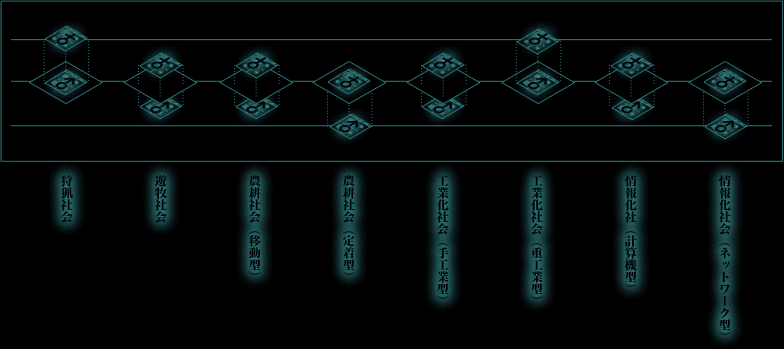BBU概論
道具を使うようになったサルが文明社会を作りあげ、BBUが発生する。そしてなぜか「男性の方が女性よりビンボーゆすりをする」という現象が起こる。この章では社会進化とBBUについて考察する。
道具を作るようになったサルが、生きるために最初にしたことは「狩」であった。棍棒や弓といったアタッチメントを使い、外の生物を殺し、食料とした。しかし、社会が進化し人口が増えてくると、「狩」という自然からのその場かぎりの搾取では、集団を養えなくなる。そこで「遊牧社会」が登場する。アタッチメントを「棍棒」ではなく「ムチ」におきかえて、動物の集団をコントロールし、育て、そこから清算される乳や毛といった資源を利用しつつ、最終的には殺して食べる、というしくみを作った。
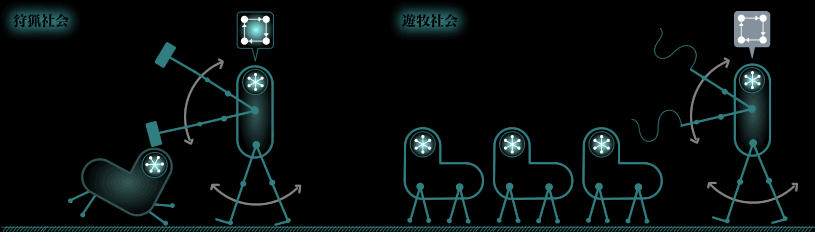
狩猟・遊牧社会が「動物依存型」なのに対し、農業社会は「植物依存型」である。初期の農業社会は「焼き畑農法」である。森を焼いて平らにし、かつ「灰」という肥料を手に入れる。そして「鋤」というアタッチメントで土を掘り起こし、植物を育てた。しかし人工が増加してくると、せまい面積でたくさんの作物を育てる必要がでてくる。家畜を育て、その糞を肥料とし、アタッチメントを再び「ムチ」におきかえ、「鋤」を取り付けた家畜をコントロールした。これにより、焼き畑ができなかった荒地をも耕地に改良することができた。
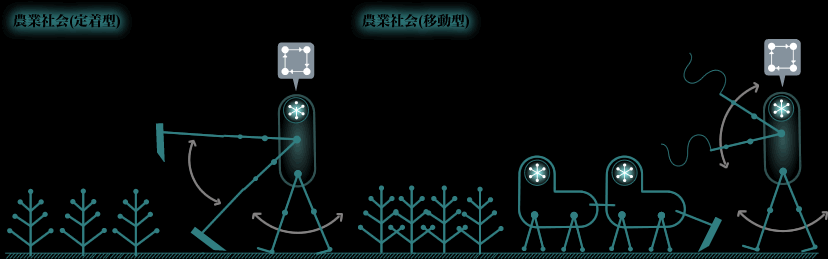
「機械」というアタッチメントが登場すると、さらに社会は変化する。最初の機械は水力や風力といった「自然エネルギー」で動いた。それを人間がコントロールし、生産を行う「手工業」であった。しかし化石燃料、とりわけ「石油エネルギー」が発見されると、「発動機」を持つ機械が登場する。この機械は大きな振動を作り出すことができた。さらに「発動機」から「発電機」へと進化すると電気エネルギーが登場し、それをコントロールする「スイッチ」という新しいムチで、人間はたくさんの機械を制御し、さらに生産性をあげることができるようになった。
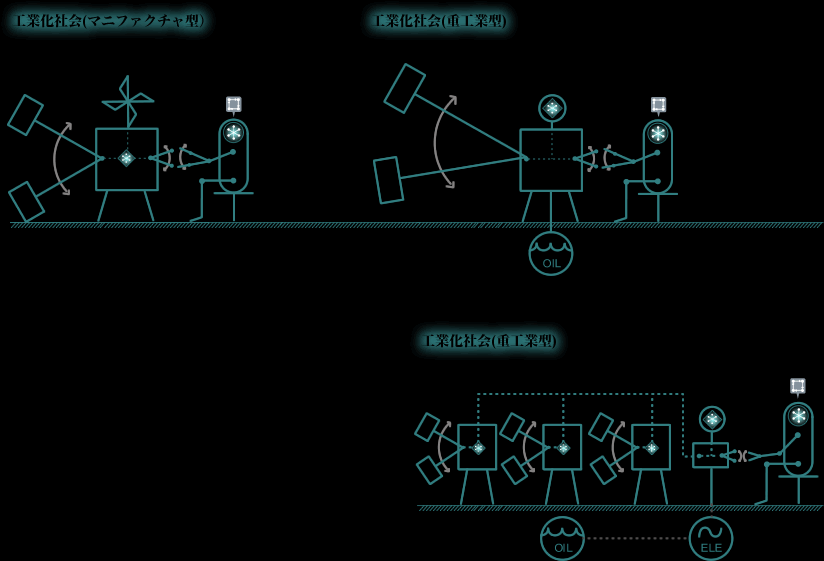
機械はさらに進化し、たくさんのスイッチと電気を応用して「計算機」を作り上げある。計算機は、それまでの肉体運動を拡張するアタッチメントではなく、脳の処理を拡張するアタッチメントであった。そしてその計算機が、同じくスイッチと電気を応用して作った「通信機」と合体することでネットワーク社会が生まれる。この社会は人間のアイデアプロセッサーの「シミュレーション」の部分が拡張されたいった。
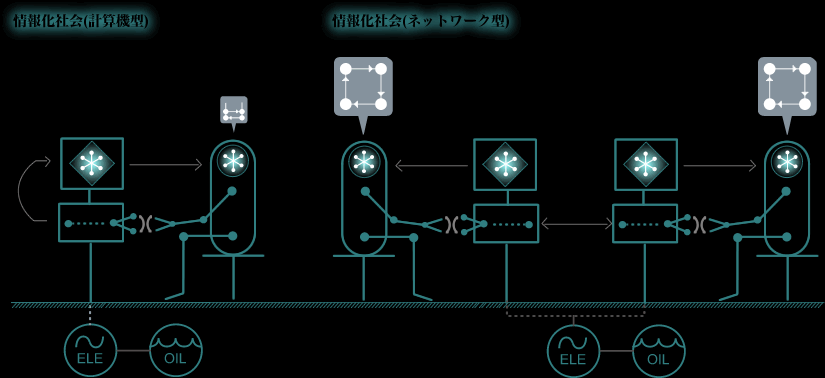
これまでの文明社会の変化から、人間の部分だけを抽出した図が上図である。これを見ると、工業化社会で増えた労働パターンが「座り(SIT)仕事」である。ここでは人間の「考える」というプロセスを機械が代行してくれたので、アイデアプロセッサーの作動が必要なくなる。しかし、情報化社会になると、ふたたびアイデアプロセッサーを使う「座り仕事」がふえてくる。これは通信機によって人間どうしがつながってネットワーク環境が生まれ、対人間に対して価値を作っていく産業が発達したためである。
これらの図の全体を眺めると、あきらかに狩猟社会から情報社会に向けて、身体的な運動量が減り、そのかわり脳を使う仕事は増えている。脳を使う仕事とは、シミュレーションである。そこが拡張すると、現実世界とのズレも拡大する。これは、第二章で説明した「GAP」の発生を生みやすい。さらに情報化社会のオフィスワークは、座り仕事が多い。これは足がまったくフリーになっている状態である。「GAP」の発生と、足のフリー、この二つが重なって、現代社会は歴史的にみて、もっともビンボーゆすりが発生している時代となっている。
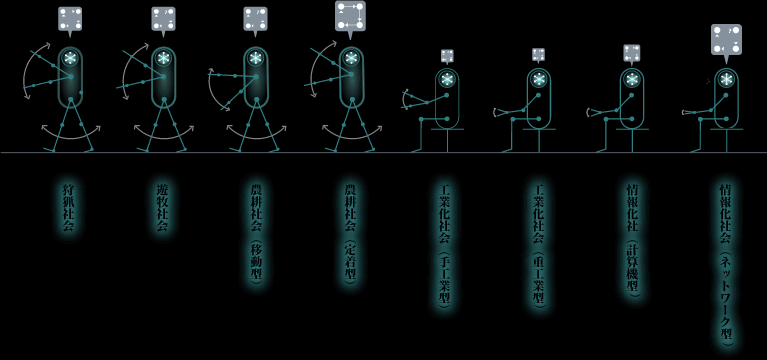
BBUが発生しやすい現代、なぜ「男の方がビンボーゆすりをする」という現象が見られるのだろうか?
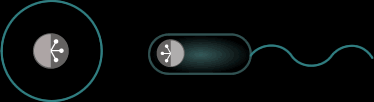 男性と女性の違いを考えとき、根源的には生殖細胞の違いに行き着く。卵子と精子という生殖細胞を比較して一番大きな違いは、精子には振動を起こす「鞭毛」というアタッチメントが着いていることである。つまり「オスは生殖細胞のときから振動している。ゆえにBBUの発生が高い」と強引に言い切ることもできるが、それではあまりに単純なので、もう少し考察を進める。
男性と女性の違いを考えとき、根源的には生殖細胞の違いに行き着く。卵子と精子という生殖細胞を比較して一番大きな違いは、精子には振動を起こす「鞭毛」というアタッチメントが着いていることである。つまり「オスは生殖細胞のときから振動している。ゆえにBBUの発生が高い」と強引に言い切ることもできるが、それではあまりに単純なので、もう少し考察を進める。
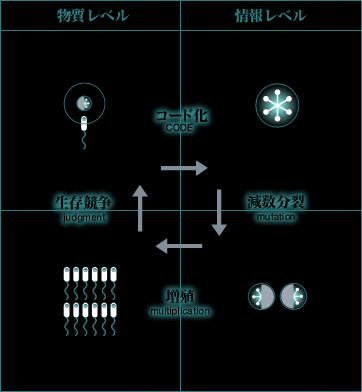 卵子と精子のもう一つの大ききな違いは、その数である。女性が一生で使える卵子の数が400個から500個に対し、成人男性の場合、一日に4000万個から5000万個も作られる。図は精子と卵子の行動をバイオプロセッサーに当てはめたものである。コードとしてのDNAは、減数分裂によって、遺伝情報を二分の一にする。これは人間の遺伝子は二組あり、子供は父方と母方から半分づつ遺伝子をもらうというシステムのためである。
卵子と精子のもう一つの大ききな違いは、その数である。女性が一生で使える卵子の数が400個から500個に対し、成人男性の場合、一日に4000万個から5000万個も作られる。図は精子と卵子の行動をバイオプロセッサーに当てはめたものである。コードとしてのDNAは、減数分裂によって、遺伝情報を二分の一にする。これは人間の遺伝子は二組あり、子供は父方と母方から半分づつ遺伝子をもらうというシステムのためである。
そしてオスの半分の遺伝情報だけが増殖し、精子が大量に作られる。そして、メスの半分の遺伝情報は卵子となり、子宮の中で待機状態となる。精子は、その卵子に向かうのだが、ここで大問題が起こる。
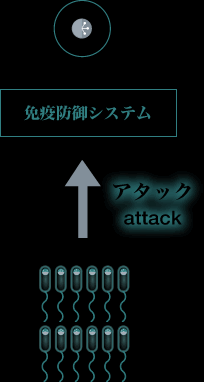 メスの体の免疫システムは、精子を異物とみなし、総攻撃をかけてくるのである。しかし精子にとっては「死」を意味する「アタック(ATTACK)」を、卵子にたどり着くために行わなければならない。
メスの体の免疫システムは、精子を異物とみなし、総攻撃をかけてくるのである。しかし精子にとっては「死」を意味する「アタック(ATTACK)」を、卵子にたどり着くために行わなければならない。
生存の確率が低いもかかわらず、精子がアタックをするのは、そうした判定を自ら受けることで、物理的振動や生物的振動に耐えうる、新しい個体を残すためである。そうして卵子にたどり着いた一匹の精子は卵子と受精し、受精卵となり、成長し、生物個体となる。やがてその個体は、生きてきた肉体をふたたびDNAという情報に還元する作業を行う。
ここで重要なのは、卵子はアタックをしない、ということである。競争をせず、受け入れ先として待機している。そして受精後の成長、育成という大仕事のために、むしろアタックより環境との「協調 ハーモニー」を選ぶ。
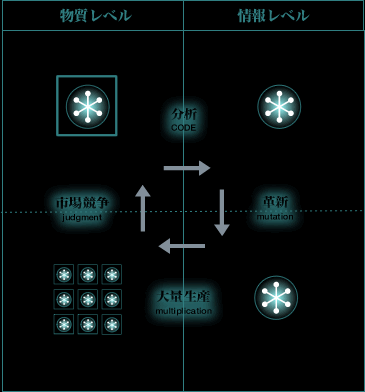 この精子がアタックをするモデルは、生物全体にも当てはめることでき、とりわけ20世紀の資本主義経済では、経済の競争原理を説明するために利用された。上図は資本主義社会の市場競争のモデルである。「大量生産、市場競争、データ化、新製品開発」という4つのプロセスになっている。
この精子がアタックをするモデルは、生物全体にも当てはめることでき、とりわけ20世紀の資本主義経済では、経済の競争原理を説明するために利用された。上図は資本主義社会の市場競争のモデルである。「大量生産、市場競争、データ化、新製品開発」という4つのプロセスになっている。
男性は、「空を飛びたい」といった欲求にみられるように、物理的に絶対不可能な状況に、挑戦してしまう本能がある。これは「アタック」だ。太平海を単身ヨットで渡る冒険家、月へ行こうとするロケットエンジニア、放射能をコントロールしようとする核開発の科学者。女性から見ると、無謀としか思えない行動を起こす。
しかしアタックをしかけた多くの男性が、「空から墜落した死ぬ」。死なないために、男性は、構造的思考と、肉体的労働で、機械というアタッチメントを作り、実現する。資本主義社会を発達させたのは、機械文明を生んだ、この男性原理である。
しかし石油で動く機械は大量の商品を作り、その生産資源の確保のために植民地戦争が起こり、今度は石油を燃やして巨大な兵器たちがアタックを繰り返して世界大戦を起こしてしまった。これは、男性の持っているアタックの本能が、石油というエネルギーと、機械というアタッチメントを得たばっかりに、そこだけが暴走した結果である
男性にBBUが多いのは、本能的に実現不可能なことにアタックするため、理想と現実のズレが起こり、「GAP」が発生するからである。無理だ、とあきらめたオスは「負のBBU」を発生させ、ときにはそのストレスで自殺をする。そして、果敢にアタックを行うオスは「正のBBU」を発生させ、環境を生き抜く新しいアタッチメントを作ろうとする。それはときに「冒険」と呼ばれ、アタックをしかける前の振動、俗に言う「武者震い」も、「正のBBU」に近いものである。
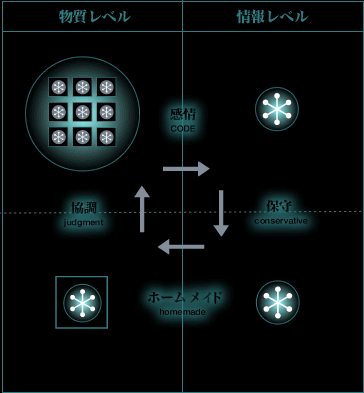 さてここで、さきほどの競争原理モデルのまったく逆を考えたのが下図である。「競争ではなく協調」、「分析ではなく感情」、「開発ではなく保守」、「大量生産ではなく、ホームメイド」となる。競争原理モデルが、男性的であるのに対し、この協調モデルは女性的である。
さてここで、さきほどの競争原理モデルのまったく逆を考えたのが下図である。「競争ではなく協調」、「分析ではなく感情」、「開発ではなく保守」、「大量生産ではなく、ホームメイド」となる。競争原理モデルが、男性的であるのに対し、この協調モデルは女性的である。
競争原理モデルは、その内部に「死」や「破壊」というものを抱えているのに対し、協調モデルは、「生」や「育成」がある。そしてこれを社会に置き換えると、競争モデルから出てくるのは「商品とゴミ」であるが、協調モデルから出てくるのは、「エコ、ロハス、リサイクル、ボランティア」といった、社会運動である。
現在の資本主義軽罪は、UGC(user-generated content)にみられるように、これまでの競争モデルにこの「協調モデル」を組み込もうとしている。それは、20世紀の男性原理の競争モデルが、世界大戦という悲劇を作り、戦後は環境破壊という現象を起し、構造そのものに問題を発見したからである。
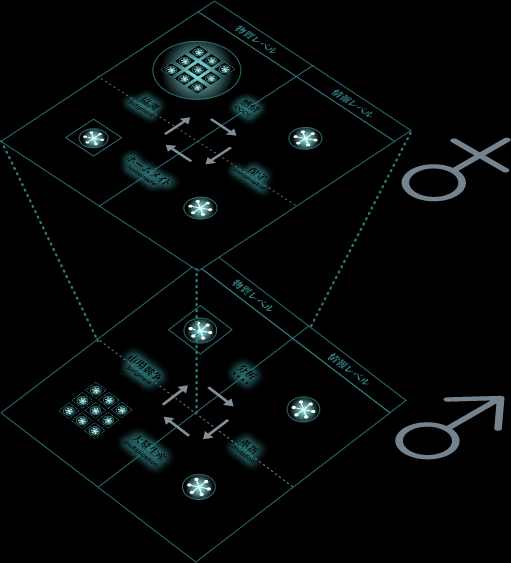
これまでの文明社会の各時代を、母性、父性の、どちらが強いかで分けたものが上図である。男性原理の狩猟社会から、女性原理の農耕社会、そして再び男性原理の工業化社会から、現在は女性原理が主流になりつつあるネットワーク社会へ。このように母性社会と父性社会が交代する現象は、動物では見られない。
現代は母性社会への移行期であるが、いまはまだ男性の競争原理で経済は動いており、その中で仕事をする女性も増えてきた。情報化社会は、脳の内的世界を拡張するので、GAPが発生しやすく、社会進出した女性の中には、ストレスで男性なみにBBUをする女性の数も増えていくことだろう。そして男性は、本能的にもっている「アタック」の欲求を、母性社会の中でいかに「正にBBU」として発散するか?という問題にとりくまなければならないだろう。