BBU概論
BBUとは振動である。そして広く考えれば、それは「生物の振動」である。それに対し宇宙には、生物ではない振動、「物理的振動」がある。この章では、宇宙進化、生物進化の流れを追いながら、振動とBBUについて考察する。
宇宙は振動に満ちている。ミクロな世界では、原子や電子は「回転運動」という振動をしている。そのミクロな回転体が集まった物質は、音波や電磁波などの波の振動を生み出す。そして物質が集積してできた巨大な惑星も回転・公転をし、その惑星が集まった、銀河系も回転という振動をしている。そもそもこの宇宙そのものが、膨張、収縮という、人間から見れば、とてつもなくゆっくりな周期の振動をしている。こうした宇宙の物質たちが根源的に持っている振動が、「物理的振動」である。電子のスピンや、惑星の公転を簡単に止めることができないように、物理的振動は、永続的な「安定した振動」である
その宇宙の中に「地球」という星が生まれた。「地球」がほかの惑星と違っていたのは、「水」が大量にあることだった。水はその姿を「液体、固体、気体」と変化させて地球に充満している。水の気体である雲は、宇宙からくる紫外線などの振動が地表にふりそそぐことを防ぎ、反対に地球の熱エネルギーが、宇宙へ赤外線として逃げていくことを防いだ。水の集合体である海は、海流によって地表の熱のかたよりを均質にし、固体である氷は、熱を貯めたり放出したりすることで、一年を通しての気温の変化も均質にした。水は地球を「エアコンが効いて、宇宙からの騒音(物理的振動)から守られたホテル」のような星に変えた。
そしてその地球で、一番守れた、最高級のホテルが、液体の水の集合した「海」であった。地表では拡散してしまう物質も、海の中では、ちょうど水に溶かした油が集合するように、水が持つ表面張力でまとまった。それは「ホテルに集まった泊り客」のようだった。海は、地球の自転により潮の満ち引きというリズムや、風により寄せては返す波というリズムを作り出し、集まった物質という泊り客に、子守唄のようにそのリズム(振動)をずっとずっと聞かせ続けた。
そしてある日、その物質たちが、突然自力で振動を始めた。その振動は、それまで宇宙に存在しなかった新しい振動だった。「生命」の誕生である。生命は地熱や太陽のエネルギーを使って「生物的振動」を行った。しかしそれは、物理的振動にくらべて水の泡のように、あまりにもはかなく、すぐに消えてしまう「不安定な振動」であった。もしこのときの生命に意思というものがあったら、「この振動を止めてなるものか」と思ったであろう。それは生物的振動を続けていこうとする力、つまり「生命力」というものであった。
物理的振動は、安定した振動であり、日本語で「律動」、英語では「バイブレーション」という。それに対し、生物的振動はとても不安定な振動であり、日本語では「拍動」、英語では「ビート」という。生物的振動は、物理的振動からエネルギーをもらうことで振動を続けることができるが、ときには物理的振動から攻撃をうけ、振動を消されてしまうこともある。
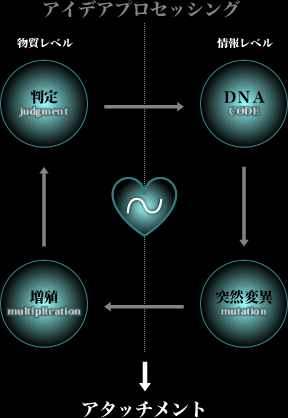 生命は、その「不安定さ」を逆に利用し、その振動を継続するためのシステムを作り上げた。誕生し、成長するが、すぐに壊れてしまう、という不安定なサイクルは、見方を変えれば、多様な新しいシステムを次から次へと「試し撃ち」できるということであった。
生命は、その「不安定さ」を逆に利用し、その振動を継続するためのシステムを作り上げた。誕生し、成長するが、すぐに壊れてしまう、という不安定なサイクルは、見方を変えれば、多様な新しいシステムを次から次へと「試し撃ち」できるということであった。
生命は振動を止めないため画期的戦略を編み出した。その振動を「分裂」によって、どんどん増やしていく、という方法だった。もし環境からの影響で、一部のグループの振動がとまっても、これなら別のグループは振動を続けることができる。2の2乗、つまり幾何級数的手法で、爆発的にその数を増やす方法、それを「増殖」という。振動が振動を増やしていく「増殖」は、物理的世界ではありえない現象であった。
しかし宇宙からの紫外線や放射線のような強い振動、急激な温度変化などの物理的振動は、増殖で増えた「生物的振動」をいやおうなしに攻撃する。「生命」はそうした試練によって、「生きるか、死ぬか」という「生き残りの審判」を受ける。ほとんどの生命はこの審判で「死」、つまり生物的振動のストップとなる。
そこで生命はひとつの戦略を編み出した。生命の振動のパターンを、一度すべてコードという「情報」に変えてしまう、という奇想天外な手法だった。生命は物質でできているので、物理的振動を受けやすいが、それを「情報」に変換してしまえば、いつまでもその振動を保存できることができる。これは楽器に例えると、例えばあなたがピアノで「ド・ミ・ラ」という鍵盤を押したとしよう。するとちょっと悲しげな「短調の響き」という「振動」が聞こえる。この振動は時間が経てば減衰し、やがて消えてしまう。しかしそれを「Am」というコードで記述しておけば、いつまでもその「短調の響き」は記録され続ける。このように生命は、その「生きている響き」を、物理的振動の影響を受けにくい、「DNA」というコードで記録するという方法を編み出したのである。
しかし、物理的振動は、この「情報」をも攻撃する。紫外線や放射線といった震動は、このDNAを攻撃し、そのコードの一部を判別できない情報の並びに変えてしまう。しかし、それは生命にとっては「思う壺」であった。生命はその「情報」をもとに、アミノ酸とたんぱく質を使って、「ニュータイプ」の生物的震動を作りだす。これを「突然変異」という。そのニュータイプは、増殖によって爆発的に増え、そして「生き残りの審判」を受ける。そのとき死んでしまうこともあるが、ときにはそのニュータイプが、オールドタイプよりも頑丈で、新しい生物的震動として生き残ることがあった。
こうして生命は、「増殖」「審判」「コード化」「変異」というサイクルをひたすら繰り返し、より頑丈な生物的震動を生み出していったのである。そして地上の生物があふれはじめると、今度はその生物的震動そのものが、生物的振動を攻撃するという自体も発生してきた。生物が生物の「生き残り審判」をすることを「生存競争」という。生物が、DNAのコードを攻撃し、その一部を書き換えることを「感染」という。感染は「ウィルス」という、生物と物質の間のような存在が作り出した。これらの現象は、さらに生物的振動のバリエーションを増やすこととなった。
新しい生物的振動を生み出すシステムを、「バイオプロセッサー」と呼ぶことにする。このバイオプロセッサーの結果として、さまざまな工夫が、「器官」として生物の体に「アタッチメント(装着)」されていった。その中でとくに独創的だったのが「脳」と「モノを作る手」というアタッチメントであった。
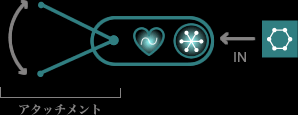 もっとも原始的な生命の「器官」は「移動器官」がある。もし生命が動くことができなければ、物理的振動から逃げ出すことができず、すぐに死んでしまう。また自分の栄養となる物理的振動=食物に近づいていくこともできない。生命のビートを続けていくためのは、「なんとか逃げる」「なんとか食べる」ための工夫がいる。バイオプロセッサーで作られた、初期の簡単な移動器官は、「繊毛」や「鞭毛」という、振動構造だった。
もっとも原始的な生命の「器官」は「移動器官」がある。もし生命が動くことができなければ、物理的振動から逃げ出すことができず、すぐに死んでしまう。また自分の栄養となる物理的振動=食物に近づいていくこともできない。生命のビートを続けていくためのは、「なんとか逃げる」「なんとか食べる」ための工夫がいる。バイオプロセッサーで作られた、初期の簡単な移動器官は、「繊毛」や「鞭毛」という、振動構造だった。
その後、魚のような「尾ひれ」ができたり、「足」ができたり、「羽」ができたりして、生命はどんどんその移動距離を広げていった。こうした生命の機能を拡張する器官を、生命の「アタッチメント」と呼ぶことにする。
生命はバイオプロセッサーで、さまざななアタッチメントを生み出し、その生きる範囲を広げていった。水を掻くヒレの振動、地面を歩く足の振動、空を飛ぶ翼の振動。極寒の南極の氷の中から、高温の火山の噴火口の近くまで、地底深くから、空の上まで、ありとあらゆる場所に生命はあふれていった。このことを、ちょっと地球の外から見てみよう。このバリエーションにとんだアタッチメントを「アイデア」に例えるなら、地球はそのアイデアを作り出す、巨大な「アイデアプロセッサー」ということになる。それは、「物理的振動」と「生物的振動」がうまくバランスをとることによって生まれる。 宇宙でももっともいろいろな振動が響き渡る、にぎやかな振動の星となった。
脳は、もともとどんどん増えていく生物のアタッチメントを統括するための「アタッチメント」として誕生した。脳がなければ、生命は「食物を目というアタッチメントで見つけて、足というアタッチメントにつないで近づく」というプロセスを行うことができない。生命のアタッチメントの数が殖え、そのしくみが複雑になればなるほど「脳」は大きくなっていった。
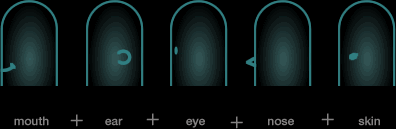
しかし逆に言えば、脳はそれらのアタッチメントにしばられ、「自由」ではなかった。体の各器官をつなぐ神経の信号塔でしかなかった。「脳」の生物における場所も、体の中心ではなかった。典型的な哺乳類の体のモデルは以下のようなものである。この場合、脳をささえているのは、「首」である。脳の近くにはできるだけ外界からの信号を取り入れるアタッチメント「目、耳、舌、鼻」が近い方が、貴重な神経細胞のケーブルを使わなくてすむ。そこで頭部にはそれらのアタッチメントが集合する。もし脳を大きくしようとすると、首を太くしなければならない。これでは、これらのセンサーアタッチメントをすぐにその反応する方向へ向けることができない。ならば、体の上にのせる方がまだいい。こうして「馬型」のスタイルが生まれる。しかしそれでも脳を大きくしていくと、体の重心が前に集まることになる。
サルが住む樹上は、天敵もいなく、そしてたくさんの木の実や虫や葉っぱがあふれる世界であった。まさにそれは、なんの苦労もなくても食事が手に入る、夢のような世界であった。樹上生活をするサルは、気にぶら下がるために前足が大きくなっていった。そして脳は、まるでハンモックの上のスイカのような位置に収まり、体全体における体積を大きくすることができた。
ところが地球の気候の変化による環境の変化は、森を砂漠へと放り出した。そのとき、サルの中に、「生きなければならない」という、生命のビートが鳴り響いた。生きるためには、
エレメント(物質界)→ コード(情報界) → 物質化作業(物質界)→ 生き残り判定(物質界)→ コード化
を行わなければならない。しかし、今回はそんなことをしていたら死んでしまう、せっぱつまった状態だった。ここでサルがとても幸運だったのは、その体のスタイルだった。「脳」を肥大化させてもなんとかささえられる。さらに、モノを作るための「手」が自由である。このことがものすごく重要だった。それはなぜか。
- 「脳の肥大化の保障」は、物質ではなく、情報による思考錯誤、シュミレーションを可能にする、ということであった。
- そして手が自由であるということは、アタッチメントを生命の「いけにえ」を出さずに、物質を使って作ることができる、ということである。
画期的な手法をとる生命が誕生する。それは「アタッチメントを作る地球のシステムそのものを、アタッチメントとして装着する」という、とんでもない生き物だった。
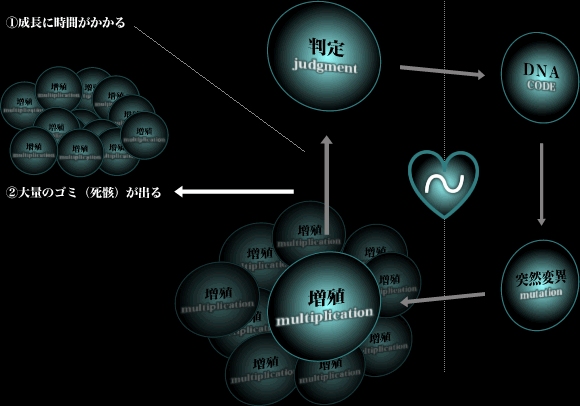
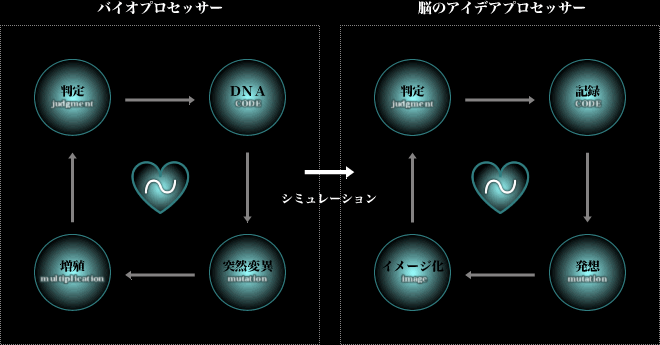 さて、バイオプロセッサーでどこが効率が悪いかというと、「プロトタイプ→生き残り」という判定を、一匹の生命の世代を犠牲にしておこなわなければならない、ということである。それはとても時間がかかることであるし、たくさんの生命の「死」によって成り立つものである。もしかりに、このアイデアプロセッサーと、とてもよく似たシステムを、物質ではなく情報そのもので組み立てることができたら、その試行錯誤の時間を、圧縮できるのではないか。これは「情報」による物質界のシュミレーションである。
さて、バイオプロセッサーでどこが効率が悪いかというと、「プロトタイプ→生き残り」という判定を、一匹の生命の世代を犠牲にしておこなわなければならない、ということである。それはとても時間がかかることであるし、たくさんの生命の「死」によって成り立つものである。もしかりに、このアイデアプロセッサーと、とてもよく似たシステムを、物質ではなく情報そのもので組み立てることができたら、その試行錯誤の時間を、圧縮できるのではないか。これは「情報」による物質界のシュミレーションである。
このシュミレーションが正確に行えたら、大量の死骸と、「成長の時間」というムダをなくすことができる。
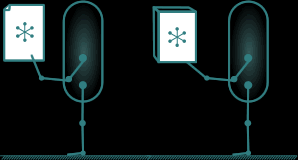 人間はそれを「道具」を使うことで、トカゲが空を飛ぶ鳥に進化するまでの時間よりも、ずっとずっと短い時間で、人間は空を飛ぶことができた。
人間はそれを「道具」を使うことで、トカゲが空を飛ぶ鳥に進化するまでの時間よりも、ずっとずっと短い時間で、人間は空を飛ぶことができた。
二足歩行というスタイルは、「脳」によって思考すること(THINK)、「足」によって移動すること(TRANSPORT)、「手」によってモノを作ること(MAKE)を 促進した。そして歩き疲れた人間は、夜になれば、再び動物のように地面に寝転んだ。
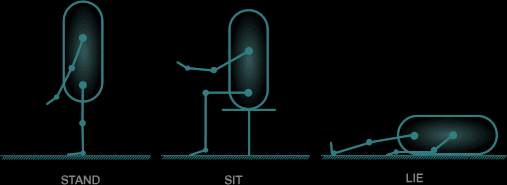 そしてあるとき人間は「二足歩行」と「寝転ぶ (lies down).」との中間の状態、つまり、「座る(sits down).」という状態をキープするための道具=「イス」を作りだした。イスは、思考すること、手によってモノを作ることを行いつつ、足を重力から開放した。そして脳がクリエイティブな思考を始めるとき、その振動の影響をうけて、体重を支える必要のなくなった足は、純粋に振動することが可能になった。こうして、地球上にはじめて、BBU=ビンボーゆすりが発生したのである。
そしてあるとき人間は「二足歩行」と「寝転ぶ (lies down).」との中間の状態、つまり、「座る(sits down).」という状態をキープするための道具=「イス」を作りだした。イスは、思考すること、手によってモノを作ることを行いつつ、足を重力から開放した。そして脳がクリエイティブな思考を始めるとき、その振動の影響をうけて、体重を支える必要のなくなった足は、純粋に振動することが可能になった。こうして、地球上にはじめて、BBU=ビンボーゆすりが発生したのである。
そして、そのBBUを加速させる道具が登場したのである。
それが「イス」だ。
